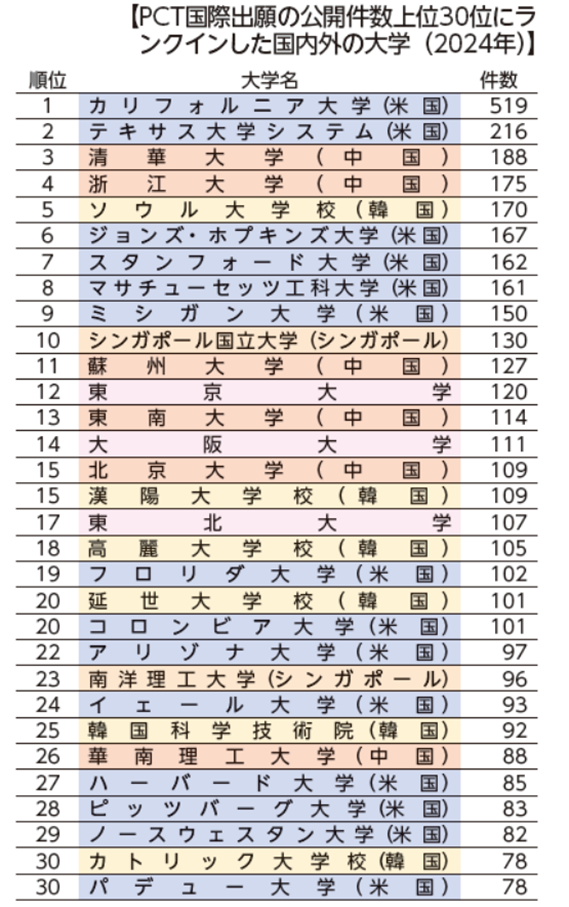世界知的所有権機関(WIPO)は、2025年11月12日付け「世界知的財産指標2025年次報告書」を公表した。2024年において、特許と意匠の出願件数は増加したが、商標の出願件数は横ばいであった(下記表参照。)。
| Applications worldwide | 2023 | 2024 | Growth rate (%) |
|---|---|---|---|
| Patents | 3,552,300 | 3,725,000 | 4.9 |
| Trademarks | 15,249,000 | 15,228,300 | –0.1 |
| Designs | 1,525,600 | 1,559,400 | 2.2 |
同報告書によれば、特許出願件数は、2024年では過去最高の370万件の出願があり、2023年に比べ4.9%増、5年連続の伸びである。中国、インド、韓国、日本の大幅な増加が主な牽引役となった。中国は2024年に180万件の特許出願し、2023年より9%の増加であった(世界シェア49.1%)。米国603,194件、日本306,855件、韓国246,245件、欧州特許庁199.402件であった。上位20カ国で2桁成長したのは、インド(+19.1%)、フィンランド(+15.4%)、トルコ(+14.6%)の3か国のみであった。2024年には、アジアは世界の製造業の中心地としての地位を更に強化し、世界中で出願された特許出願の10件中7件がアジアの知的財産庁で処理されることとなる。
[所感]アジアの特許出願件数の世界シェア及び伸び率から見ると、アジアが世界の製造業センターになる。特に、インドの知財動向に留意する必要がある。
2025年11月13日記